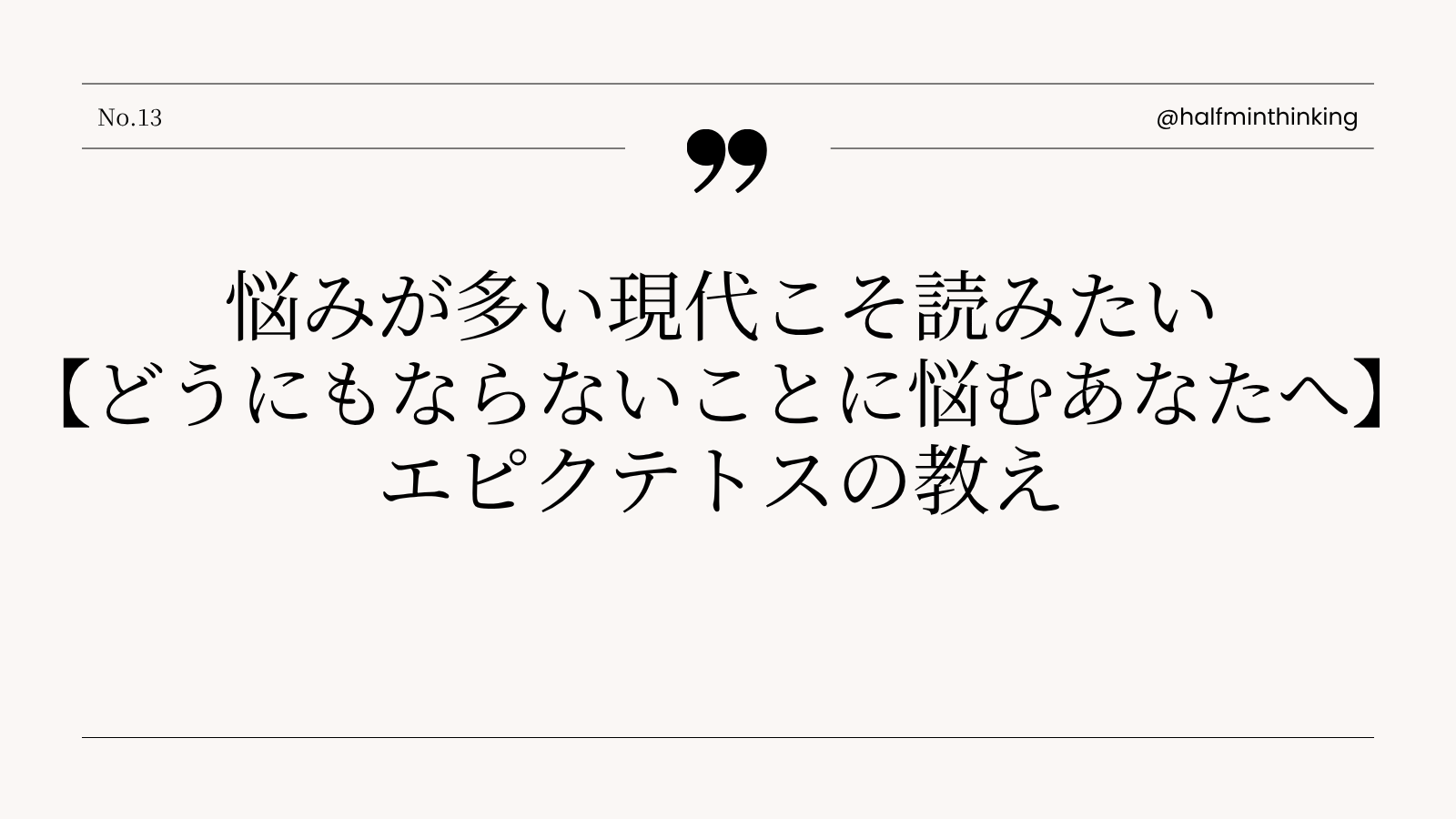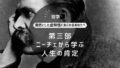> 「我々を混乱させるのは、物事そのものではなく、物事に対する我々の意見である」
この言葉は、今から約2000年前、ローマ帝国で奴隷として生きた一人の哲学者が遺したものです。彼の名は、エピクテトス。彼は、生まれながらにして自由を奪われ、足が不自由になるほどの過酷な扱いを受けながらも、その精神だけは誰にも隷属させることなく、ストア派の哲学者として多くの人々に影響を与えました。
なぜ、最も不自由な環境にいたはずの彼が、誰よりも「精神の自由」について語ることができたのでしょうか。
この記事では、エピクテトスの壮絶な人生を辿りながら、彼が「どうにもならないこと」に満ちた世界で、いかにして心の平穏と自由を見出したのかを探求します。彼の教えは、情報や環境に振り回されがちな現代の私たちにとって、力強い「心の羅針盤」となるかもしれません。
## 奴隷から哲学者へ
エピクテトスの生涯は、逆境そのものでした。彼は生まれながらにして奴隷であり、その主人は皇帝ネロの側近という権力者でした。ある逸話では、主人が気まぐれに彼の足を捻り上げ、エピクテトスは「おやめください、旦那様。そのうち折れてしまいます」と静かに言ったと伝えられています。そして、足が折れた後も、彼はただ「だから言ったでしょう」とだけ言ったといいます。
この逸話の真偽は定かではありませんが、彼の哲学の核心を象徴しています。つまり、自分の身体ですら、自分ではコントロールできない「外部のこと」であるという厳しい現実認識です。
幸いにも、彼は哲学を学ぶことを許され、その才能を開花させます。奴隷から解放された後、彼はローマで哲学塾を開きますが、皇帝によって追放され、ギリシャのニコポリスでその生涯を終えるまで、質素な生活の中で教えを続けました。
## コントロールできることと、できないこと
エピクテトスの哲学、そしてストア派の哲学の出発点は、非常に明確な区別から始まります。
**「我々の力の及ぶこと(コントロールできること)と、力の及ばないこと(コントロールできないこと)を区別せよ」**
– **力の及ぶこと**: 自分の意見、意欲、欲望、嫌悪など、我々の内面で起こること。
– **力の及ばないこと**: 自分の身体、財産、評判、地位、他人の行動など、我々の外側で起こること。
彼は、幸福な人生を送るための秘訣は、この区別を徹底することにあると言います。私たちは、コントロールできない外部の物事に一喜一憂し、心を乱されることで不幸になります。雨が降るのを嘆いても、他人の評価を気に病んでも、それはエネルギーの無駄遣いです。
私たちが本当に力を注ぐべきなのは、唯一コントロール可能な、自分自身の内面だけなのです。
> 「幸福への道はただ一つしかない。それは、我々の力の及ばない物事について悩むのをやめることだ」
## 役割を演じるように生きる
では、コントロールできないことばかりの世界で、私たちはどう生きればよいのでしょうか。エピクテトスは、人生を「劇」にたとえます。
> 「覚えておけ、汝は劇の俳優であり、作者(神)が望む役を演じているのだと。短い役なら短く、長い役なら長く。作者が汝に貧乏人の役を望むなら、それを立派に演じよ。足の不自由な役、役人の役、市井人の役でも同様だ。汝の仕事は、与えられた役を立派に演じることだ。役を選ぶのは、別の者(神)なのだから」
この考え方は、私たちに大きな安らぎを与えてくれます。私たちは、自分の「配役」(生まれ、容姿、才能、環境)を選ぶことはできません。しかし、その与えられた役を、いかに「立派に演じるか」は、私たち自身の選択に委ねられています。
貧しい役なら、卑屈になるのではなく、誇り高く演じる。困難な役なら、嘆き悲しむのではなく、勇敢に演じる。その「演じ方」こそが、私たちの価値を決め、精神の自由をもたらすのです。
## 読後感にかえて
エピクテトスの言葉は、優しく慰めてくれるものではありません。むしろ、それは厳しい現実を直視し、その上で、人間としての尊厳を失わずに生きるための、力強い哲学です。
彼の生涯は、どんな逆境にあっても、人間の精神は自由でありうることを証明しています。物理的な自由がなくても、心の自由は誰にも奪うことはできないのです。
先の見えない現代社会で、私たちはしばしば、自分ではどうにもならないことに悩み、無力感を覚えます。そんなとき、エピクテトスの言葉は、私たちに問いかけます。
「それは、君がコントロールできることかね?」と。
そして、もしそれがコントロールできないことならば、悩むのをやめ、自分にできること、つまり、自分の意見や行動に集中するようにと促します。
彼の哲学は、諦めではありません。それは、限られた力しか持たない人間が、それでもなお、幸福で、気高く生きるための、最も現実的で、最も力強い「生き方の技術」なのです。